 悩んでいる人
悩んでいる人面接最後に「何か逆に質問ありますか?」ってよく聞かれるけど、
これってホントに何でも聞いていいのかな?
何か効果的な質問とかってあるのかな?



いわゆる「逆質問」ですね。
複数の企業で採用責任者を務めた私が解説しますね!
・逆質問が設けられる4つの理由
・効果的な逆質問3選
・逆質問で注意すべきポイント
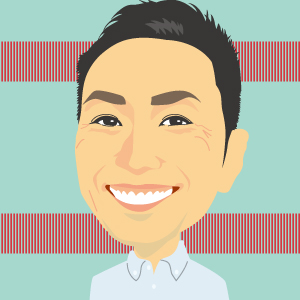
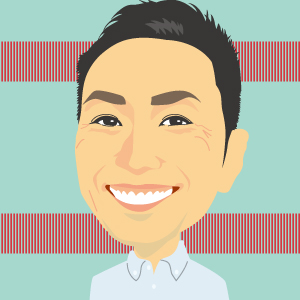
- 株式会社オモワクの創業者
(転職エージェント) - 自身も4回転職を経験
- 3社で採用・人事責任者を経験
- 約10,000人と面談・面接を実施
Twitter: 福尾 翔/ワクワク転職エージェント@FukuOsho
今回は、だいたいどんな面接でも最後に設けられる通称「逆質問」について、
大手企業からベンチャー企業にて採用の責任者を務めてきた経験をもとに解説していきます。
ネットにも様々情報が記載されていますが、実際面接をしてきた身としてやや違和感を覚えることもあるので、
よりリアルな情報をお届けできればと思います。
先出しすると、この逆質問だけで面接全体の評価が爆上げすることはありません。
一方で、逆質問によって全体の印象がマイナスに働くことはよくあるので、最後まで気を抜かないようにしましょう。
それでは、前置きはこの辺りにして、早速解説していきますね!
逆質問が設けられている4つの理由
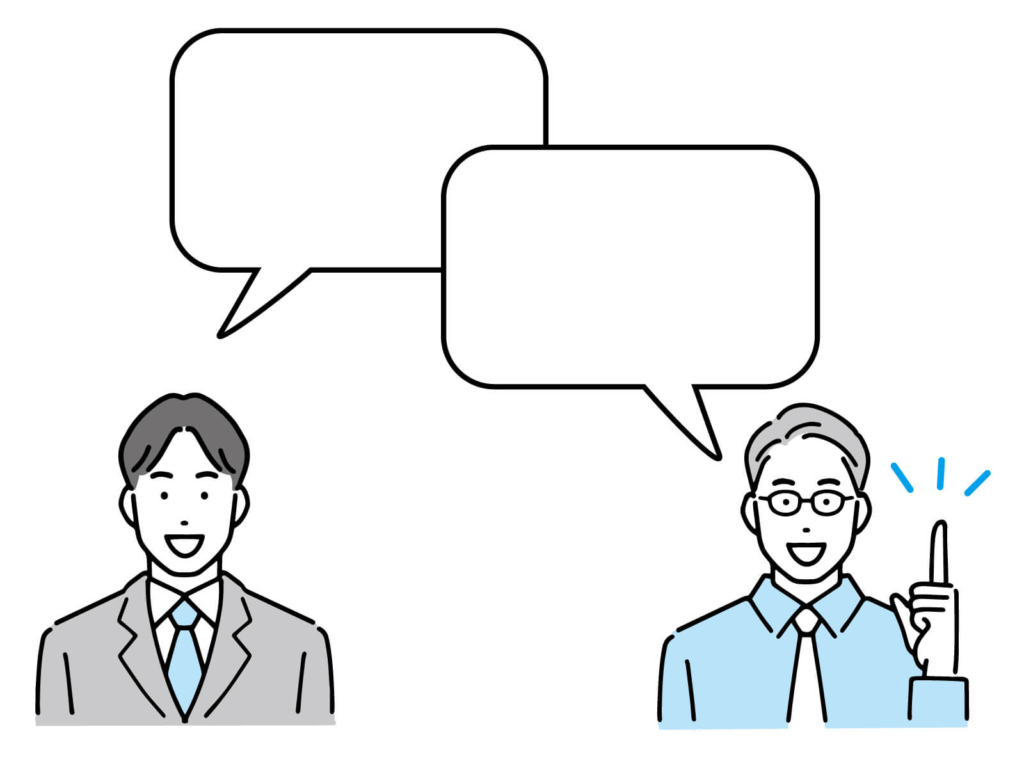
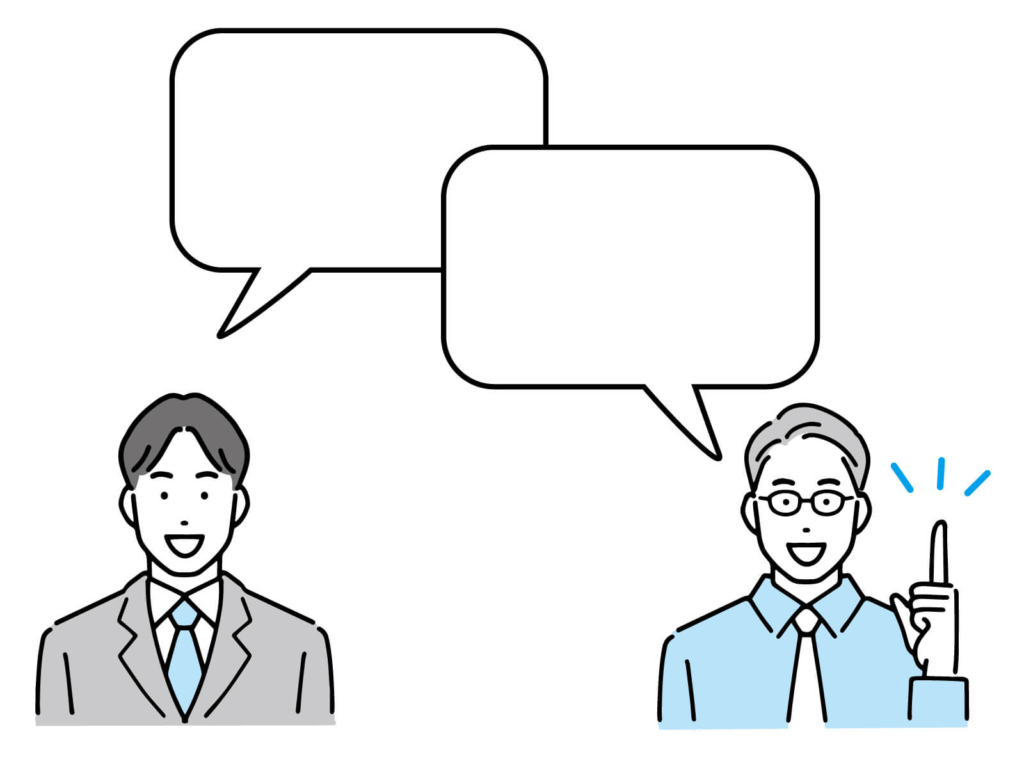
そもそも、なぜ面接の最後に「何か質問はありますか?」という逆質問の時間が設けられているのでしょうか。
私が面接官だった時も、1時間の面接の中でどんなことを質問するかあらかじめ決めた上で臨んでいましたが、
最後10~15分は逆質問の時間として確保していました。
1時間のうち、10分だと全体の1/6、15分だと1/4とかなり多くの時間を割くことになります。
もちろんそこには意図があります。
①求職者の疑問点や懸念点の解消
②自社への意欲、志望度合いの確認
③価値観や志向性などのマッチング確認
④求職者に対する魅力付け
大きくは以上の4点になります。まずはこれを理解すること、そして、理解した上で効果的に立ち回るための方法を解説していきます。



あれ?他の記事で「コミュニケーション能力」を確かめるって
書いてあったけど違うの?
そうですね。正直なところコミュニケーション能力はここまでの面接でのやり取りで十分把握できます。
むしろ、最後の逆質問でしかコミュニケーション能力が判定できないような面接は面接官の力量不足と言わざるとえません。
(1問1答のような質問形式でしょうか)
①求職者の疑問点や懸念点の解消
個人的にはシンプルにこの点が大きかったです。
面接は双方理解の場であるので、一方的に質問して終わるのではなく、
求職者の方からも疑問点があれば聞いていただき、認識のGAPが起きないように努めます。
どうしても求人票だけだとわからないことも多いため、
気になることがあれば何でも聞いてもらいたいと私自身もシンプルに思っていました。
ただ、よく言われるように、少し調べればわかるようなことばかりだと、
「自分で調べる力」に懸念を感じることも正直あります。
まずはご自身で調べ、それでもわからなかったこと、確認したいことについて質問してみましょう。
②自社への意欲・志望度合いの確認
私が数多く面接官をする中で結構このような回答をされる方がいらっしゃいました。
この場合、多くの面接官は
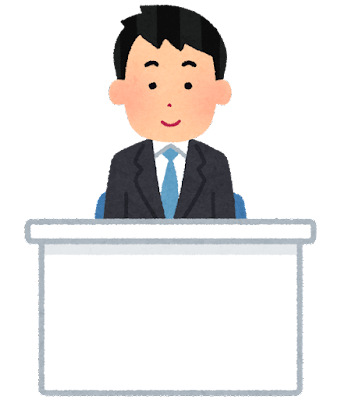
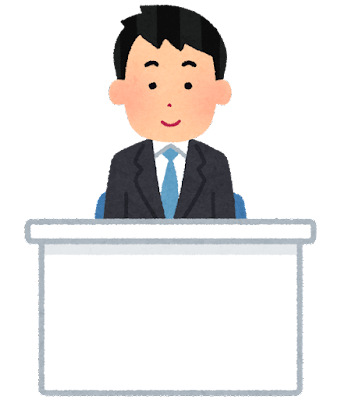
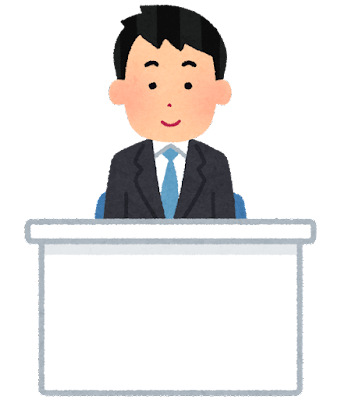
あれ、うちに興味ないのかな…?
このように感じることがあります。
もちろんそれだけで不合格になることはないと思いますが、少しでも興味があるから選考を受けているわけであって、
その想いや熱意を伝える絶好の場だということを覚えておいた方がいいかと思います。
特に20代の転職においてはスキル・経験があまり高くない場合がほとんどなため、
想いや熱意をどれだけ伝えられるかが大きなポイントになってきます。
③価値観や志向性などのマッチング確認
逆質問でいただく質問をざっくり大別すると
- 業務的なこと
- ご自身のこと(仕事へのスタンスなど)
に分けられると思います。
やはり質問する=大事なことを確認するということなので、
どのような質問をされるかによってその方の仕事に対する考え方や向き合い方についても垣間見ることができます。
(もちろんこれだけで判断はしませんが)
休日や残業時間→仕事とプライベートのバランスをどのように考えているのか?
教育制度などの育成について→手取り足取り教えてほしいのか、裁量持って働きたいのか?
昇給や賞与→役職や給与を優先して働きたいタイプ?
など、あくまで前後の文脈により変わってくるので一概には言えませんし、
それぞれ大事にしたいことが異なるので良いとか悪いとかの判断ではありません。
あくまで、会社のカルチャーや目指すビジョンと一致しているか?
ということを面接で仰った内容と併せて確認したいのです。
面接では「積極的に業務を覚え、いち早く成長していきたいです!」と言っていたものの、
残業についての質問が多かったら「あれ?さっき言ってたことは本心だったのかな?」と感じることも多くあります。
④求職者に対する魅力付け
一通り面接をする中で、「ぜひ次の選考に進んでいただきたい」「一緒に働きたい」と感じることがあります。
その場合、出来るだけ自社への志望意欲が高まるように、面接官も頑張ります。
以下のどちらの方が志望意欲が高まりますでしょうか。
・笑顔も少なく淡々と面接が進んだ
・逆質問しても短文の回答で終わった
・明るく、自分の話を興味深く聞いてくれる
・逆質問の回答も質問した内容から膨らませて様々なことを教えてくれた
言うまでもありませんがケース2の方が印象がいいですよね。
ただ単純に決まったことを質問する、逆質問への回答も卒なくする。
これだけだと面接を通して自社への魅力を高められません。
だからこそ、企業側の魅力を伝えるためにも求職者の想いや価値観が色濃く現れる逆質問を設定しています。
効果的な逆質問 3選





逆質問をやる理由はわかったけど、
何か効果的な質問ってあるの…?
どんな会社・面接官においても「これを聞けば必ず評価が上がる質問!」というのは残念ながらありません。
代表的な3つの項目に沿って解説していきます。
①具体的な質問
②面接官本人への質問
③自分と似た境遇の人についての質問
①具体的な質問
抽象度の高い質問だと、何を知りたいのかがぼやけてしまい、答える側も抽象度が高くなってしまいがちです。
自分が知りたいことを確認するためにも質問を具体的にするようにしましょう。
- 会社の将来性を教えてください
- 業界のトレンドとして●●が増えておりますが、御社も同様の展開・取り組みをお考えでしょうか?
Yes→同業他社との差別化ポイントを差し支えない範囲で教えていただけますでしょうか。
No →それでは、メインの事業を伸ばしていくための取り組みや、新たな施策等あれば教えていただけますでしょうか
企業は常に成長していくために様々なことを検討・実行しています。
「将来性」と一括りにされると多くの観点があり、時間の関係からも浅い情報しか得られません。
業界トレンドや会社理解を踏まえた具体的な質問をすることで企業研究をしているというアピールになります。
- 会社の雰囲気を教えてください
- 御社のHPを拝見しましたが、若手社員が多く活気のある社風だと感じました。
現在応募させていただいている●●部の方においてはどのような社員の方がいらっしゃいますでしょうか?
会社には多くの社員が在籍しています。それをまとめた「雰囲気」となると「明るい」「まじめ」などの総評となってしまいます。
だからこそ、自分が入る部署に絞ってみたり、仕事への取り組み方など具体性を持った質問をすると得られる情報が多くなります。
面接官からしてもイメージしやすいので回答がしやすくなります。
②面接官本人への質問
個人的には「効果がある」質問としては面接官本人に対しての質問がオススメです。
会社に関する質問というのは面接官もよく聞かれているので、他の人と差別化を図ることで効果的に映ります。



面接官本人への質問…?
面接では基本的に「あなた自身」のことを聞かれます。
なので、あなたも質問のベクトルを「企業」ではなく「面接官」へと向けてみましょう。
- ●●さん(面接官)はA社で働く上でやりがいに感じていることはどのようなことですか?
- ●●さん(面接官)の思う、A社の好きな点/改善していきたい点はどのようなことでしょうか?
- ●●さん(面接官)がA社にて長年働き続けている理由は何でしょうか?
このような質問をされると、面接官は自分自身のことを話すことになるので、ついつい熱が入ってきます。
そうすると話が盛り上がったりすることもあり、勝手に満足度が上がることに繋がります笑
ちょっとしたテクニックですが効果的な質問なので活用してみてください。
面接官自身について質問をし、面接官が熱く話したらその話に追加で質問を被せるとさらに効果的です。
逆にせっかく熱く話してもらったのに「あ、はい、わかりました」と卒ない対応をすると逆効果にもなりかねませんのでここはご注意を。
③自分と似た境遇の人についての質問
中途採用で入社した社員を大きく分類すると3つに分けられます。
・未経験の職種からの入社
・異業界から同職種にて入社
・同業界・同業種からの入社
自分自身と同じ境遇にて入社した社員についての質問をすることで、意欲の高さをアピールすることに繋がります。
- 私と同じように未経験で入社した方で、活躍される方の共通点はございますでしょうか?
- 私と同じように異業界から入社した方で、初めにつまづきやすい点はどのようなことでしょうか?
- 私と同じように同業界から入社した方を見る中で、注意したいいポイントなどがあれば教えていただけますでしょうか?
企業側が不安に思っていることを先読みした質問となるため、
入社後に頑張ってもらえそうだという意欲が伝わりやすくなります。
入社前の質問ではなく、入社後の質問へと視点が切り替わるため、他の候補者との差別化を図ることができます。
差別化=印象に残るということになるので、効果的な質問になるでしょう。
逆質問で注意すべき3つのポイント


ここまで、なぜ逆質問が設定されているのか、その中で効果的な質問について解説してきました。
次は逆に注意した方がいいポイントについて説明していきます。
① 調べればすぐにわかることは質問しない
② 福利厚生ばかりの質問にならない
③ あらかじめ質問は3~5個用意しておく
①調べればすぐにわかることは質問しない
よく言われることですが、HPや求人票に記載されていることを質問するのはネガティブに映ってしまします。
もちろん、HPや求人票に記載はあるものの、内容が少しわかりにくいものであれば質問しても問題ありません。
注意した方がいい代表的な質問をまとめました。
・年間休日は何日ですか?
・どんなサービスを扱っていますか?
・御社の企業理念を教えてください
このままの質問の仕方はNGですが、少し工夫することで効果的な質問にも変化します。
・御社の〇〇というサービスを拝見しましたが、競合サービスと比較した際に優位性はどのような点でしょうか
・企業理念の〇〇に共感いたしました。この理念を社員に浸透させるための取り組みについてお伺いできますか
あくまで、「会社のこと調べてないな」と思われると印象が悪くなるので、
「調べたよ」ということが伝われば質問自体は問題ないです。
事前にHPと求人票は細部まで確認した上で、それが伝わるような質問を考えましょう。
②福利厚生ばかりの質問にならない
福利厚生についての質問自体が悪いということではありません。
転職理由の一つに「労働環境の改善」を考えている方もいらっしゃるでしょう。
ここで重要なのが福利厚生ばかりの質問にならないということです。
会社のビジョンやそれに紐づく事業内容、カルチャーと求職者の考えやスタンス、実績などのマッチング度合いが高いことがいい採用になります。
福利厚生も大事ではありますが、そればかりになると自分の働きやすさ>会社の目指すこととなってしまいネガティブに映ってしまいます。
・有休取得のしやすさについて教えてください
・平均残業時間を教えてください
・離職率はどれくらいですか?
福利厚生については転職エージェントを通じて確認することが一番オススメです。既に持っている情報の共有や追加でうまい具合に企業に確認してくれるので、使わない手はありません。
福利厚生についての質問は転職エージェントにかくにんしてもらうのが吉。
③あらかじめ質問は3~5個用意しておく
面接の流れの中で、もともと聞こうと思っていたことが明らかになることがよくあります。
そうすると最後の逆質問の際に「…ありません」となってしまう可能性がありますよね。
そうならないために、あらかじめ3~5つの質問を準備しておきましょう。先ほど記載した「効果的な質問」を参考に考えてみてください。
また、質問数が多すぎるのもあまりよくありません。面接時間が伸びてしまう可能性があり、次の予定に影響が出てしまいかねません。
基本的には2~3個質問をするために、3~5個質問を準備しておくことをオススメします。
「特にありません。」を避けるために事前に考えておきましょう。
効果的な質問の項目で記載した「面接官本人への質問」は鉄板項目ですね。
まとめ


今回は面接の最後に聞かれる「逆質問」について解説してきました。
まず逆質問時間が設定されている理由を理解し、その上での効果的な質問について、また注意すべきポイントを抑えることで相手からの見え方が変わります。要点だけ再度記載しますので、面接前に復習してもらえると幸いです。
①求職者の疑問点や懸念点の解消
②自社への意欲、志望度合いの確認
③価値観や志向性などのマッチング確認
④求職者に対する魅力付け
①具体的な質問
②面接官本人への質問
③自分と似た境遇の人についての質問
① 調べればすぐにわかることは質問しない
② 福利厚生ばかりの質問にならない
③ あらかじめ質問は3~5個用意しておく
今回はここまでとなります。
難しいことはありません。1つ1つ着実に身に着けて臨んでいきましょう!

